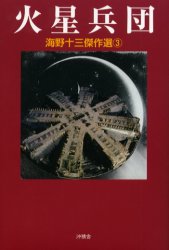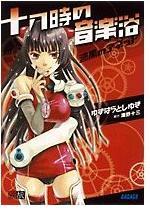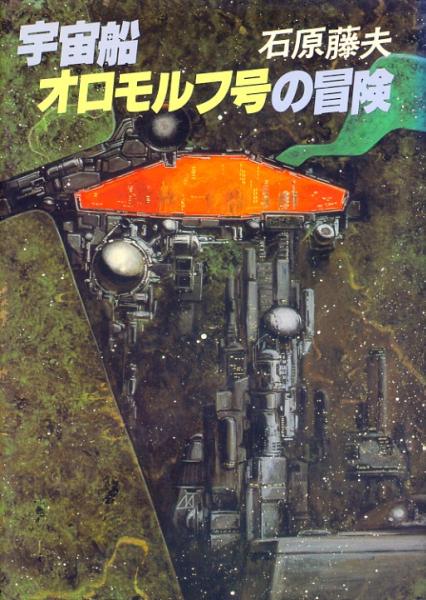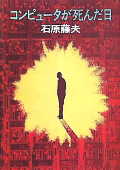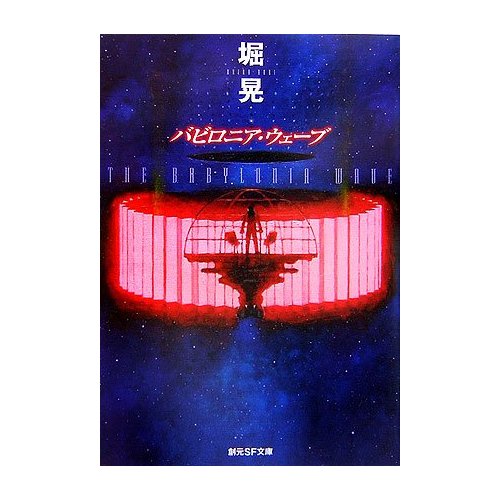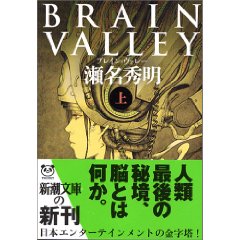ハードSFはご存知の通り、綿密な科学考証に基づいたSFの1ジャンルの事で、ストーリーの骨格となるアイデアが、論理的かつ科学的に説明可能なもの。大雑把にいうと理科系向きの小説といったところでしょうかね。
20世紀に入ってアメリカで勃興したSF小説自体が”空想科学小説”と和訳されていた位だから、まあ好きな人にとっては「ハードSFこそがSFの源流であーる!」と主張するんでしょうね。 では、私が読んだ(読もうとしている)作品でイチオシを紹介しましょう。
石原藤夫(いしはらふじお)
1933年生 東京都在住 工学博士玉川大学教授(専門は電気通信工学) 1965年に「高速道路(ハイウェイ惑星)」でSFマガジンでデビューする
宇宙船オルモロフ号の冒険
(ハヤカワ文庫JA 今は絶版・・・オークションとかで入手可能)
物理的な建造物である宇宙船自体が微分可能という、純粋な数学を題材にした長編。単なるガジェットとしての数学ではなく、ストーリー展開が数学そのものといったところ。数学という学問自体が抽象的なので、内容もよくわからん展開になるけど好きな人にとっては面白いもの。 オルモロフ号が巨大な宇宙船で、乗組員は人間、サイボーグ、知性と感情を持つロボットなど様々で、宇宙を旅して冒険するという設定。(設定は宇宙船ビークル号の冒険をリスペクトしている。もちろん題名も) 旅の途中でわけのわからん知性体と出会い、時には戦いを経ていく。主人公がたぶんサイボーグだったかな? 数学を専門としている人で有能なロボット助手と一緒に様々な難問を解決していくもの。難問はまさに数学そのもので、異星の知性体が船内に侵入したときに残した編微分方程式を、独自の推理で導出した境界条件で解いて解決し、敵対する生命体をやっつけるというもの。ストーリを面白くさせているのが、宇宙船内の人間(ロボットもいるけど)関係もからめた組織の理不尽さに翻弄されながらも知力でこれを克服するところで、日本の大企業や官庁に良くある上層が自己保身した考えていないような非合理的で馬鹿げた組織を揶揄している。多分旧電電公社研究所に居た作者自身の体験を元にしているのだろうなー。 結構過激なのが理不尽な理由で主人公が宇宙船内の軍法会議みたいなところで「死刑」を宣告されて執行されるのだけど、なんとも石原藤夫らしいアイデアで切り抜けるラストは実に面白い。 巻末には考証に使った数学の解説がある。ある空間の特異点をオルモロフ号が周回することで積分状態になるとか・・ 理科系大学の2,3年生くらいで習う解析数学が題材になっているので、基礎知識が怪しい(私もそうだけど)人向けにストーリー展開を補完するようなものですね。
画像文明
(ハヤカワ文庫JA 1976年)
マスコミュニケーションが「テレビ」という画像情報を中心とした現代(といっても作品が発表されてから30年以上たつけど)を演繹して、個人レベルのコミュニケーションが画像情報を介して行われるようになった近未来を描いた短編。
コンピュータが死んだ日
東京ベイエリアに建造された超巨大コンピュータが首都圏のインフラを管理している近未来を舞台設定とした長編小説。この巨大コンピュータの「意図的な」プログラム欠陥(?)で、コンピュータが管理している東京湾の石油コンビナートが突然大爆発を起し、都心部が壊滅状態になるところから始まる。惨事に巻き込まれた主人公の情報科学スペシャリスト(フリーランスのSEに近い)が、混乱する東京エリアで家族を救い出す前半部と、政府が緊急設立した事故原因究明プロジェクトに編入されて惨事を引き起こした犯人を突き止める後半部で構成されている。 1980年初頭に書かれたもので、今となってはかなり古臭いガジェットになってるけどもストーリーは実に面白い。犯人を追い詰めるプロジェクトチームの活動は、推理小説とは全然違う内容で、当時(1980年代)に始まったシステムエンジニアリングの思考方法を応用し極めて論理的に展開させていく。(ちなみに2008年現在でいうSystem Engineeringとはかなり異なっている)
堀晃(ほりあきら)
1944年生 関西在住 繊維メーカの技術職として働く傍ら執筆を続けてきた。 1970年に「イカルスの翼」でSFマガジンでデビューする
バビロニアウェーブ
太陽系近傍に謎のエネルギー収束が発見された。レーザー光線のようなコヒーレント光で、バビロン王朝くらいの太古の昔から存在していた(?)ということでバビロニアウェーブと命名された。この光束は非常に大きなエネルギーを持っており、このエネルギーを地球に送る事で人類のエネルギー問題は大幅に改善された。しかしある日そのエネルギー送信に問題が生じ、調査に向かう。そして意外な結末が判る。 多分、この作者の最初で最後の長編小説。
梅田地下オディッセイ
複雑に絡み合いながら増殖する大阪市梅田地区の地下街。ある日この地下街が地上から完全に隔離され、閉じ込められた人々が脱出を試みるも失敗。地下街の中に住み着き小規模なコミュニティをいくつか形成し、対立しあう。主人公はどのコミュニティにも属さない男。地上では冴えないサラリーマンだった。その男と、閉じ込められた地下街で会ったゆきずりの女との間にできた新生児は、驚くべき能力を備えていた。外界と地下街を遮断したのは”誰か”の意思なのか?
瀬名秀明(せなひであき)
1968年生 宮城県在住 理学(医学?)博士東北大学の教職員が本業。 1995年に「パラサイトイブ」でデビュー。
ブレインバレー
脳科学を専門に研究する特別プロジェクトがつくば研究学園都市に設立され、研究者として招聘された主人公の孝岡は、同じく脳外科のエキスパートとして招聘された米国の女性医師と一緒に、臨死体験としたという謎の女性を被検体として研究を続けるが、どうにも説明できない超常現象が次々と発生する。そしてラストでこの特別プロジェクトの真の目的が明らかにされる。 生命科学、認知工学、生物社会学、情報工学などのいろいろな学問を凝縮した内容で、物語の大半が学術解説になっているようなもので、ハードSF好きには堪らない本でしょう。いわゆるてんかん気質の医学的な考察を詳細に解説しているところなどはなるほどと頷く。でもストーリーが平凡という酷評もありますけどね。私は好きです。 それと、内容が非常に専門的なので作者自身がこの小説の解説本を執筆しているそうです(私は読んだことはないが)